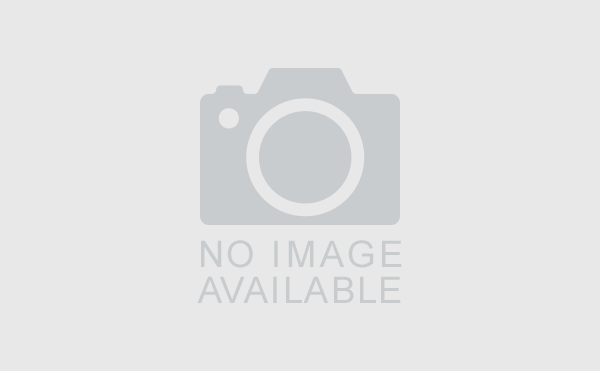<今日の一枚と一句>「その38(2025.08.13~08.26)」

【 濁る川 帰省展墓や 犀星碑 】(にごるかわ きせいてんぼや さいせいひ)
金沢市内を流れる犀川は、水嵩が増し濁った流れ、川沿いを歩くと「ごうごう」とした音が聴こえてきます。
普段はさほどの水量もなく、所々に堆積してできた小島?が現れて、小さな草木が茂る場所もありますが、これらが全て水没していて・・・。
「室生犀星碑」が犀川大橋の上流(写真の手前反対側)に向かって左側に建てられています。そこに3人の家族連れが写真撮影中でした。
会話の内容からすると、父親が金沢出身で今は別の地域に住んでいて、子供の夏休み期間中にお墓参りを兼ねて金沢に帰省し、市内を散策している様子。
金沢市内の「お盆」を7月15日とする家が多いと聞くが、全国的に「お盆休み」と言えば8月15日前後、有給休暇や特別休暇を取得することが多い・・・。
たぶん、お墓参りを済ませた帰り道に「碑」の説明と父親の幼き頃の思い出を子に語る場面もあったのだろう・・・・と。
※1「展墓」: 「盂蘭盆(うらぼん)に墓参りをする」ことで、秋の季語
※2「室生犀星碑」: 先に投稿の文参照
《2025.08.13撮影・投稿》
《お願い》
【以降、各ブロックの画像を表示するには、ここを「CLICK」と表示した箇所を「CLICK」してください】

【 古き良き 看板みたり 盆休み 】(ふるきよき かんばんみたり ぼんやすみ)
橋場町の三叉路近くに「枯木橋」があります。すぐ傍の緩い坂を登ると「光画社」という歴史ある写真館の建物が現れます。
その角を左折すると、とても古い看板が「卯建=宇立=うだつ」のある屋根上に掲げられていて、ガラス越しには白黒TVなど昭和の懐かしきものが展示されています。
特に説明があるわけでもなく、たぶんお店だったであろう雰囲気があります。通りすがりの観光客のワンショット風景に時々出会います。
市内には古い「金沢町家」や「商店」が今も多く残っていて、「ぶらり散歩」に出かけた際には、その歴史的価値の高い建物にも出会います。
霞んでしまった看板の文字からすると、建築関係の店舗又は関連の建屋だったのかなと思いますが、道行く人に「昭和の雰囲気」を見せてくれているのかなと思いましたが・・・。
※1「盆休み」: お盆(8月15日前後)の休暇
※2「枯木橋」: 先に投稿の文参照
※3「金沢町家」: 先に投稿の文参照
※4「卯建=宇立=うだつ」: 隣家との境に「防火壁」や「プライバシー」を守るために設置
《2025.08.14撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 水澄や 映えて内堀り 海鼠壁 】(みずすむや はえてうちぼり なまこかべ)
金沢城内三の丸広場から「鶴の丸休憩館」方向に向かって東西に延びる城壁があります。「切り石積み」の石垣の上にある「海鼠壁=なまこかべ」と共に内堀に映っています。
この海鼠壁の説明は先に投稿しましたが、漆喰壁の模様が海にいる「海鼠=なまこ」に似ていることから付けられた呼び名とか。
外見上からは想像できませんが、内側にまわると、「鉄砲狭間」が隙間なく並んでおり、いざという時には「隠し狭間」として威力を発揮する仕掛け(鉄砲がどこから出てくるのかわからない恐怖もある)があります。
お盆の時期の入城者は、日本人より外国人の方が圧倒的に多い印象です。(日本人はお墓参りに出かけて?)
今日は「終戦記念日」、この先、この金沢城(「無血城」)のように戦いのない平穏無事の時が流れていくことを祈ります。
※1「水澄む」: 秋になって透明度が高くなる水面の意(秋の季語)
※2「隠し狭間」: 鉄砲狭間が隠れて見えなくした仕掛け
※3「無血城」: 城内に戦による流血がない「戦いの無い」(平和)様子
《2025.08.15撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】


【 塔の灯が 消えて送り火 五山かな 】(とうのひが きえておくりび ござんかな)
今日は京都の伝統行事「五山送り火」があります。市内の主だったビルなどが照明を落とすと、東山如意ヶ嶽に「大の字」が点灯・・・続いて松ヶ崎の西山に妙・東山に法、西賀茂船山に船形、衣笠大北山に左大文字、最後に嵯峨曼荼羅山に鳥居形が点り、ほぼ9時頃にはすべての火が燃え尽きます。
この間、JR京都駅前の「京都タワー」の灯も消され、普段見慣れた夜の景色が一変します。
1枚目の写真は昼のタワー、2枚目が夜の様子です。
そもそも「京都五山送り火」は最初に点灯する「大文字」が良く知られていることから、送り火の代名詞のように言われていますが、けっして「大文字焼き」ではありません。
お盆にお迎えしたご先祖様の霊を再び冥界にお送りする(精霊を送る)「送り火」です。
奈良市で毎年1月に行われる「若草山焼き」とは異なり、「山を焼く」訳ではありません。
昔はこの五山送り火が過ぎると「京の夏」もそろそろ終わりに・・となったようですが、最近ではまだまだ全国一、二を争う?最高気温が記録されるなど、盆地特有の暑さが続きそうですね。
※1「灯の火」: ここでは京都タワーの照明の意
※2「五山」: 文中に記載の五山
※3「若草山焼き」: 山上古墳の鶯塚に葬る霊魂を鎮めるための祭礼、供養が主たる目的(諸説あり)
《2024.11月撮影・2025.08.16投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください。】


【 朝顔や 涼風ありて 昼寝かな 】(あさがおや りょうふうありて ひるねかな)
金沢城の石川門を潜った先に「石川門休憩所」があります。ここの建屋をグリーンカーテンを兼ねた「朝顔」を毎年咲かせている風景を目にします。
お盆も過ぎると真夏日であっても、日陰では少し涼しく感じる風が吹いていて・・・。
朝が早かった「朝顔」は、もうすっかり花を閉じて、暫し休憩タイムに入ったのか?、少し元気のない姿、下を向いてゆらゆらと風まかせ(揺れています)。
陽の当たる南面に位置する「花」は元気な姿で、陰日向に咲いた「花」は下を向いて、ぐったりした様子・・・。
これまでと数値的な温度が同じでも、吹く風は少しだけ涼しくなったような感じがしてきて、季節の変化が感じられる風景・・・これからは、少しずつ秋の気配・景色へと変わっていくのでしょうね・・・・。
※1「石川門休憩所」: 兼六園側から石川橋を渡り「石川門」潜った先にある休憩所
※2「朝顔」: 夏の季語として詠まれることが多いが、涼風とすることで秋の気配と季節の変わり目を表現した
※3「昼寝」: 朝顔のぐったりした様子
《2025.08.17撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 鼠多の 橋下涼し 秋の風 】(ねずみたの はししたすずし あきのかぜ)
まだまだ厳しい暑さが続く金沢市内、広く晴れ渡った青空と照り付ける太陽は、いつまで続くのでしょうか・・。
南町に出かけた帰り道、「鼠多門橋」の下を通ると、とても涼しい風が吹いていて、しばし留まりたくなり、今まで首筋を流れていた汗を拭きました。
「熱中症アラート」が発令された午後は、人通りも少なくて・・・・。8月も下旬となれば、そろそろ秋の高い空と爽やかな空気、景色が恋しくなりました。
※1「鼠多門橋」: 2020年に再建された木製橋で、尾山神社と城の出入りに繋がる
※2「秋の風」: 「秋風=しゅうふう」「金風=きんふう」「素風=そふう」とも(秋の季語)
《2025.08.18撮影・08.19投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】


【 はやかりし 金谷出丸に 秋の音 】(はやかりし かなやでまるに あきのおと)
今日は尾山神社の裏の道を通り、甚右ヱ門坂から登城しました。歩道の吹き溜まりには既に色とりどりの「落葉」が集まり、踏みしめると足下から「秋の音」が聞こえてくるような、そんな気がしました。
このベンチは「金沢公儀用大学と鹿島建設の『建築用3Dプリンターに関する共同研究』の成果であり、一般的なコンクリートでは不可能な造形を実現しています。製作過程でコンクリート内に二酸化炭素を吸収・固定化させる技術を使用しており、カーボンニュートラル社会の達成に向けて役立つベンチとなっています。」と、「QRコード付き説明書き」に書いてありました。
普段車でよく通る道ですが、ゆっくり歩いて足を止めると、今まで気にならなかったものや風景など、まだまだ新しい発見がありますね・・・・。
※1「金谷出丸」: 現在の尾山神社
※2「秋の音」: 「秋声=しゅうせい」「秋の声」に同じ
《2025.08.19撮影・投稿》


【 待ち合わせ 異国言葉と 蝉時雨 】(まちあわせ いこくことばと せみしぐれ)
兼六園の桂坂口には、これから入園する人と、園内鑑賞を済ませた人が待ち合わせる場所として最適なのか、人だまりが良く出来る場所です。
最近の傾向として、お盆を過ぎた数日間は日本人の姿は希で、とにかく外国人旅行者を多く見掛けれる場面が多くなります。
日常的に、兼六園横に客待ちするタクシーの利用は、圧倒的に日本人の方が多いですが、今日は(日本人が少なかったことから)タクシードライバーの皆さんの手持無沙汰な様子を見掛けることが多かったよううに感じました・・・。
蝉の鳴き声が一段と大きくなり、ミンミンゼミ、ツクツクボウシ・・・多種類の蝉による大合唱・・・。 そこに幼き(人間の)子供の泣き声が加わり、何が何だかわからない位複雑な大音声合唱団の風景でした。
※1「桂坂口」: 兼六園の入出ケート、7か所の一つで最も入園者数の多い場所
※2「蝉時雨」: 先に投稿の文参照
《2025.08.20撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 日暮や 御殿見たさに 作業歌 】(ひぐらしや ごてんみたさに さぎょううた)
金沢城内に存在していた「二の丸御殿」の再建が始まって、「菱櫓」の西方向には既に櫓を大きく超える高さまで作業用の鉄骨が組み立てられていて、大型クレーンが忙しく動いてます。
城内では、今が盛りに数多くの種類の「蝉」が鳴いていて、暑い中に作業を続ける人に声援を送っている様な・・・・・・。
ひとつの鳴きが終わると、待っていたかのように次々と鳴き始め、「二の丸御殿」の完成を早く見たいと言わんばかりに、大合唱が繰り返されています。
能登半島地震の復旧復興とのバランスをとりながら、再掲計画が順調に安全に進められることを祈り、楽しみに待ちたいと思います。
※1「日暮」: 「カナカナ」と「明け方」や「日暮れ」によく鳴くことが名の由来とか
※2「二の丸御殿」: 先に投稿の文参照
※3「菱櫓」: 先に投稿の文参照
《2025.08.20撮影・08.21投稿》

【 黒門を 転げ怪しなる 落とし文 】(くろもんを ころげけしなる おとしぶみ)
今日も暑い日中でした。金沢城の黒門前にある小さい坂、木の影を選んで降ると、足元を丸まった木の葉がコロコロと落ちていきます。
丸まった木の葉の行き先が少し気になったので、よく見ると「小さな甲虫」、幼虫が生まれた後に、外敵から身を守ると同時にその葉っぱを食べて育つように、と考えられた親(甲)虫の知恵・・・。
しかししかし、このまま勢いがついて転がり続けると、坂の脇には「大手堀り」・・・たくさんの鯉が口をパクパクしています。
その昔、「巻き恋文=ラブレター」を届けたい相手の通る道にわざと落として・・・思いを伝えた様に似ていることが、虫の名の由来とか。
ロマンチックな名前をもらった「オトシブミ」、ひょっとしたら、思う相手がなかなか現れないのでイライラしながら、すぐ下の「公衆電話ボックス」まで行きたかったのかな~とも・・・・・。
ちなみに、メスが葉を包める作業は、1時間から2時間を要するが、傍でオスがその作業中ずうっと「ナンパ」されない様に見張っているとか・・・。
※1「黒門」: 金沢城の北西方向にある門の名前
※2「大手掘り」:先に投稿の文参照
※3「怪し」: 「けし=異様である」「不審である」「得体のしれない」といった意味の「古語」
《2025.08.22撮影・投稿》

【 水撒きに 小さき虹と 鬼蜻蜓 】(みずまきに ちいさきにじと おにやんま)
熱中症警戒アラートがでた金沢、金沢城内のあちこちでは各所に設置された「散水機」が大活躍でした。
左側から「タン!タン!タン!タン!」と一定のリズムで右に動き、右側の到達点に着くと、今度は「タタタタタ・・・!」とすごい速さで左に戻り、また同じ動きを幾度となく繰り返しています。
タイミングによって「小さな虹」が発生します。見る角度や太陽光により絶妙のタイミングでしか現れませんが、なぜかしらこの周辺に沢山の「オニヤンマ」が飛び交っていて、うまく散水水をかわしていました。
給水したかったのか、綺麗な虹を観たかったのかは定かではありませんが、複眼とよばれる目は、 六角形をした小さな目(個眼)が集まり、まるでマルチスクリーンのように映しだすレンズの働きをするそうで、個眼の数は一万個~三万個とも言われ、それぞれから見える映像を一つの映像として脳が認識しているとのこと。
自然界にはまだまだ「不思議な現象(解明されていない不思議)」が沢山存在しますね。
※1「鬼蜻蜓」: 日本最大級のトンボ、その形相と身体の大きさからの名前とか
※2「撮影場所」: 「四十間長屋跡」を示す立て看板付近
《2025.08.23撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】


【 空蝉の 傍木にとまりる 油蝉 鳴き飛びせぬは 何を想うて 】(うつせみの そばきにとまる あぶらぜみ なきとびせぬは なにをおもうて)
西茶屋街の小さな公園に空蝉を見付けました。 ふと目をやると傍の木には油蝉がいます。特段の動きはなく、鳴きもせず・・・。ずっととまったまま。
少し観察してみることにしましたが、全く動かない・・・同種の蝉が飛んできて同じ木の直ぐ上にとまりましたがこの蝉も同じように「鳴かず飛ばず」の様子・・・。
空蝉を見付けたからなのか、蝉たちの「お休み処」なのか、はたまた「座禅」の様な修行の場なのかといろいろ想像してしまいます。
ちなみに「空蝉=うつせみ」は、「現し臣=うつしおみ」「現身=うつしみ又はうつそみ」に通じ「この世」や「現代の人々」の意味で使われてきた(古語)。
なお、「源氏物語」に女性の名前としても登場するが、「現世は無常である」「現世は儚という意味にも。
今回は「短歌風」にて失礼しました。
※1「空蝉」: 蝉の抜け殻「虚蝉」とも
※2「油蝉」: 先に投稿の文参照
《2025.08.24撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】


【 蝋管を 櫓をこぐ如し 秋の波 】(ろうかんを ろをこぐごとし あきのなみ)
金沢市尾張町にある「金沢蓄音器館」には、600を超える蓄音器と2万枚を超えるSPレコードがコレクションされていて、異なるタイプの機器が並び、一部再生して聴くことが出来て、その異なる音色にはとてもとても感動します。
明治、大正、昭和に活躍した「蓄音器」、目と音で体験してみてはいかがでしょうか・・。
ちなみに、初めて「録音・再生」の実験に成功したのは、エジソンによって今から約150年前(1877年)、現代の音楽シーンの録音・再生技術をみてわかるように素晴らしい発展を遂げてきましたが、「音を記録に残す」夢を叶えた瞬間でもありました。
「蝋管式」や「SPレコード」は変形して「波打ち」そこに針を落とすと、まるで青く澄んだ秋の海を小舟がゆらゆらと「櫓を漕ぐ」がごとく見えてきました。
※1「蝋管式」: 中空の円筒形物体(シリンダー)の外面に音溝として刻み込んだ音源を専用機械で再生する方式
※「SPレコード」:「Standard Playing(標準演奏)用、1分間に78回転する。「LPレコード」と区別して呼ばれた。
《2025.08.25撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 秋澄や 土塀内から くしゃみかな 】(あきすむや どべいうちから くしゃみかな)
朝散歩の時間帯は少しだけ涼しくなった気がします。武家屋敷跡には、観光客の姿も見えなくてとても静かです。
大野庄用水側から鞍月用水(せせらぎ通り)にむかって歩くと、土塀の内側から大きなくしゃみがひとつ・・・。またひとつ・・・。
そのほかの音は全く聞こえてきませんが、主はここの住人でしょうか、空の青さを眺めたからなのか、はたまた「(食物)アレルギー}でしょうか・・・。
同じ小路でも季節によって目にするものや臭いや音が違っているから、足腰の鍛錬を兼ねた朝散歩が楽しく続けられるのかと。
※1「秋澄」: 爽やかに澄んだ気配、「秋気」「秋気澄む」も同意語
※2「土塀」: 武家屋敷跡を囲む塀垣
※3「大野庄用水、鞍月用水」: 先に投稿の文参照
《2025.08.26撮影・投稿》

2025年8月27日(水)から「その39」に移ります