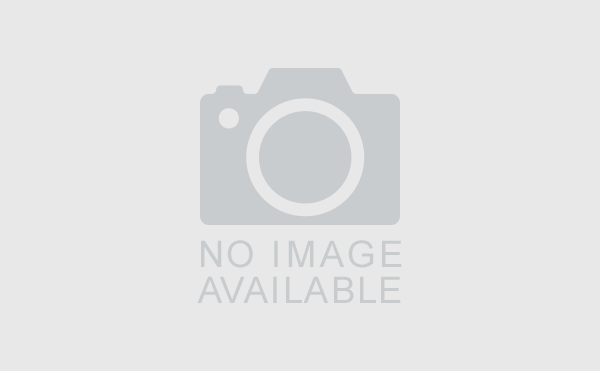<今日の一枚と一句>「その31(2025.04.30~05.13)」


【 鴨帰る 婚姻前の 前撮りか 】(かもかえる こんいんまえの まえどりか)
今日で四月も終わりました。
5月か6月(Junebride)に結婚式を迎えるのかな~と思われるカップル、結婚式前の、いわゆる「前撮り」写真撮影をされているカップルが数組いました。この黄金週間での写真撮影は、人出も多く、撮影場所を占拠するのはなかなか難しい場面もあって大変だろうと思いますが、大変なのは写真撮影のスタッフ・関係者達で、当のご両人はとても幸せそう~~終始笑顔(^^)
外国人観光客から、「これは結婚式が終わってからの撮影??」と、勘違いされる場面もありましたが、いずれにしてもハッピーなことで、この儀式は万国共通の「おめでたい」ことであることは間違いないようです。
久しぶりによく晴れて、春の清々しいそよ風が吹く「兼六園」と「金沢城」を、ぶらぶら散策してきました。
躑躅が咲き誇る城内で「菱櫓」のお堀に「ツガイの鴨」がいて、互いに見つめ合う?シーンがあり、思わず「パチリ!!」ました。
この「鴨のカップル」もたくさんのカメラマンに撮影されたことを知ってか否か分かりませんが、この後、二羽の鴨が互いに寄り添いゆっくりとした足取り???で最接近、二羽の並んで浮かぶ姿がとても印象的であり、微笑ましく思いました。末永くお幸せに~。
※1「鴨帰る」: 越冬した鴨は3月~5月にかけて、繁殖地の北に向けて一群れ(一集団)ごとにまとまって飛び立つ(春の季語)
※2「菱櫓」: 先の投稿文参照
《2025.04.30撮影・投稿》
《お願い》
【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又はタップしてください】

【 鷺苔や 城石垣と 五月かな 】(さぎこけや しろいしがきと ごがつかな)
五月の初旬からは「夏(5月5日は立夏)」、緑の美しい季節・・・。カトリックでは「聖母月」と表現されるとか。
イエスキリストの母、聖母マリアは 英語で{「Our Lady」、またフランス語で「Notre Dame」(大学名にもNotre Dame〇〇とありますが同じ意味を含む??)と呼んでいて、どちらも「私たちの貴婦人」という意味になります。
金沢城内は、(今朝の地元紙に)「金沢城赤く染め、ツツジが見頃」と、綺麗な風景写真付きで掲載記事がありました。
一方で、石川門の南側では「鷺苔(サギコケ)」が咲き始めており、石垣を背景としたアングルでの写真撮影にそろそろ似合ってくれると思います。
まだ白くひ弱な白い花に見えますが、紫色が少し濃くなると、「紫鷺苔=鷺苔の別名」とも呼ばれます。
春から夏に季節が変わるこの時期に、小さな草花や、6月から7月頃に咲く「桔梗」など、アマチュア写真家は目が離せない季節となりました。
※1「鷺苔」: 唇形の花冠が特徴、日当たりの良い少し湿った所に群生する
※2「城石垣」: ここでは石川門の南側にある石垣の意
《2025.05.01撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するにはここを「CLICK」してください】

【 陶器鯉 折り紙兜 節句かな 】(とうきごい おりがみかぶと せっくかな)
我が家の「端午の節句」、5月になると登場する「陶器製の鯉に乗った童」に「紅白の折り紙製兜」を添えて飾っています。
陶器製の鯉は、2007年に岐阜県多治見市の「陶器まつり」で買い求めたものです。
かれこれ18年間、毎年恒例の「端午の節句飾り」となっています。
昭和の時代、立派な鯉のぼりがあちこちに高く掲げられた風景が懐かしく想い出されます。
この時期、各地のイベント開催に因んだ映像がTVでも採り上げられます。
谷合にある小川の両岸を綱でつなぎ泳ぐ鯉のぼり、幾度か目にしたことがありますが、金沢の「浅野川の鯉流し」は、全国でも珍しく実際の川の中に沢山の「鯉のぼり」を入れて、流れの中を泳がせるものです。
今年は5月4日(日)の10時から15時まで開催されます。とても多くの市民や観光客が訪れることでしょう。良い天気となりますように・・・・。
※1「端午の節句」: 5月の最初の「午」の日を指す。なお、5月5日を「こどもの日」と定めたのは、1948年(昭和23年)に制定された
※2「たじみ陶器まつり」: 既に82回開催されている(今年は4月19日と20日に開催された)
《2025.05.02撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 梅ノ橋 水面に写す 鯉のぼり 】(うめのはし みなもにうつす こいのぼり)
5月4日に行われるイベント、(川の中を泳ぐ)「鯉流し」の前日、その準備は着々と進んでいました。
浅野川大橋のひとつ上流に架けられた橋「梅ノ橋」下には既にいろんな色・種類の「鯉のぼり」が川風をいっぱい受けて空中を泳いでいました。
この「梅ノ橋」は木製で独特の趣がある橋、よく映画の撮影で使われるロケーションでもあって、普段から写真撮影のスポットとなっています。
川の流れは、やや水量が不足しているようにも見えましたが・・・。本番を迎えてどのような泳ぎを見せてくれるのか楽しみになりました。
※1「梅ノ橋」: 先に投稿の文参照
※2「「鯉流し」: 5月2日投稿文参照
《2025.05.03撮影・05.04投稿》


【 ふるさとや 都忘れが 城に咲き 】(ふるさとや みやこわすれが しろにさき)
五月晴れ・・・とはいかないまでも、薄い雲間がだんだんと青く拡がってきた金沢城三の丸、ここ金沢城公園を訪れる観光客の姿も多く、朝早くから子供の歓声や異国言葉が大きく聴こえてきます。
朝のTV番組では、インバウンドの拡大にまつわる多くの影響と対策について、専門家が種々の問題点や解決方策などを真剣に議論していました。
国際的なマナーは、お国によってかなりの違いが見られます。
観光業界が潤う反面、市民が数々の迷惑・我慢を強いられる・・・日本社会全体が、将来的に外国人観光客を向かい入れるための指針の見直しや、今起きている市民生活への影響・対処方法・効果的対策の実行について急がれるところかと。
聞きなれた「金沢弁」で会話する家族?とおぼしき小グループが「お城の二の丸御殿を再建するげんて?」、「ほやほや、もう工事始まっとるんよ」、「久しぶりに城にきたけど、人が増えて
~外国人もめっちゃおおいやんね」、「京都はオーバーツーリズムで大変なんやて」、「金沢もなんか考えんと、だちゃかん」、「おいねおいね、そうなんやて」・・・・。
石川門の南東の城壁側に小さな花が咲き始めていて、まさに「野菊」のような紫の花びらの一輪を咲かせる「都忘れ」、鎌倉時代佐渡に流刑となった順徳天皇」が傷心の慰めにし、また歌を詠んだとの伝えがあるが、「都忘れ」は江戸時代以降の品種・・・もしかすると、よく似た花、別の花であった説もあります・・・。
※1「都忘れ」: 野山に咲いていた花を園芸品種として改良されたもの
※2「流刑」: 承久の乱(1221年(承久3)に敗れた天皇が流刑(後鳥羽上皇:隠岐の島に配流)となった
※3「金沢弁」: 「〇〇げんて」=「○○んだって」、「ほやほや」=「そうそう」、「だちゃかん」=「いかん」、「おいねおいね」=「うんうんそうそう」など
《2025.05.04撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するにはここを「CLICK」してください】


【 業平に 先に詠まれて 杜若 よく似て花の 菖蒲あるやに 】(なりひらに さきによまれて かきつばた よくにてはなの しょうぶあるやに)
平安時代随一の美男子でプレイボーイだったと伝わる貴族・歌人「在原業平=ありわらのなりひら)」にまつわる話は数多く、「伊勢物語」では、彼の名は伏せられ「むかし男あり・・・」と書かれている。
これは物語であることから誇張された数ではあると思うが、関係があった女性は、なんと、「3733」人とか・・・・・。
業平が都から東へ下る途中、三河国八橋に美しく咲く杜若をみて都に残してきた妻を偲んで「かきつばた」の五文字を頭として「唐衣(からころも) きつつなれにし 妻しあれば はるばる来ぬる 旅しぞ思う」と詠んだと伝わる。
金沢が生んだ三大文豪のひとり「泉鏡花」の生誕100年を記念して、昭和48年に「泉鏡花文学賞」(全国対象)が制定されて以降52回を数えます。
第48回(令和2年)の受賞作品、「小説伊勢物語 業平」(作家:高儀のぶ子氏)の本を手にし、読み始めると面白く、時間の経つのを忘れるほど・・・。
金沢城の北東にある「白鳥路」には、「杜若=燕子花=かきつばた」が咲いていて、ピンク色のツツジと紫の杜若が並んだ咲いています。
「杜若と菖蒲」・・いずれがアヤメかカキツバタと、花がよく似てはいますが、「杜若」は、花に白い筋があり、「菖蒲」は、花びらに網目模様があります。
今回は「短歌風」にて失礼しました。
※1「在原業平」: 文中記載のとおり
※2「三河国八橋」: 現在の愛知県知立市
※3「唐衣」: 「着る」などにかかる「枕詞」
※4「伊勢物語」: 平安時代の歌物語(125段あるとか)
※5「泉鏡花文学賞」: 文中記載のとおり
※6「菖蒲あるやに」: 「菖蒲」あっただろうに(なぜ「杜若」?「菖蒲」の花もあっただろうにの意(プレーボーイだつた「業平」が、ここに来て「妻」を偲ぶ「和歌」になったのか?の意
《2025.05.06撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】


【 城郭と 白を競うて 水木咲く 】(じょうかくと しろをきそうて みずきさく)
黄金週間の最終日、訪れる人の数は数日前と比べてとても少なくなりました。
金沢城の北側、四十間長屋跡の崖下からの高木に白い花が咲いて見事な景観、思わず写真撮影「パチリ!!」
この花は、「ミズキ」ですが、「ミズキ」と言えば「ハナミズキ」の方が馴染み深く、よく同じ仲間と勘違いされます。
「アメリカヤマボウシ」とも言われる「花水木」とは異なり、「水木」は、枝上に白い小花が密集した状態で咲き、遠方からみると雪を被ったように見えます。
ちなみに、ハナミズキは、明治45年当時の東京市長:尾崎行雄氏が、桜の苗木をワシントン市に寄贈した返礼として同市から贈られたとのこと。
1枚目の写真は、「河北門」から「菱櫓(西方向)」を望む位置(右中ほど)から見る「水木」で、2枚目の写真は、ツツジの上(写真の真ん中辺り)に咲く「水木」の様子です。
まだまだ彩とりどりの「躑躅」も咲いており、城散策中に足を止めたくなるロケーションかと・・。
※1「城郭」: 金沢城の城郭のこと
※2「水木」:「季語:初夏」(「花水木」の季語:春)
※3「白を競うて」: 金沢城の城壁は白色が多く採用されている。「水木」も白色で、まるで白色を競うかの如くの意
《2025.05.06撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 兼六の 園が招くか 樟落葉 】(けんろくの そのがまねくか くすおちば)
特別名勝「兼六園」は、年間250~260万人の入園者数を数えます。(コロナ禍には閉園をやむなくされましたが)石川県人口の約2.5倍の入場者数・・・人気の観光スポットの一つです。
入出口(料金所)は7か所あって、「桂坂」「真弓坂口」料金所からの入出園者は他に比して圧倒的に多く、特に土日祝日には長い行列・・・。
「桂坂料金所」から少し離れた「桜ケ岡料金所」は、観光バスの団体客の利用で、時間帯によっては多く感じられますが、これ除けば比較的空いていて、いわゆる「穴場」かと。
観桜の時期は終わりましたが、園内に植林の8200本の内「特別銘木」が19本、「重要な名木」が55本、「樹齢100年以上の古木」が354本、「その他景観木」が7770本余り・・・・・。
爽やかの五月の風が吹くこの季節には沢山の木々・草花が園へと誘います。
ここ「桜ケ岡料金所」の右手には、「クスノキ」が、葉の付け根から円錐花序を直立させて、直径5 mmほどの小さな花が多数咲いていました。
この料金所からのアクセスはお薦めです。
※1「兼六」: 兼六園のこと、詳細情報は先の投稿文参照
※2「樟落葉」: 春、芽吹きの若葉が出る時、古い葉が赤く紅葉して落葉する(季語:初夏)
※3「桂坂・真弓坂口料金所」:「桂坂」は金沢城に最も近く、「真弓坂口」は「21世紀美術館」に最も近い料金所
《2025.05.07撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 足踏みや 蓮華躑躅が お庭かな 】(あしぶみや れんげつつじが おにわかな)
加賀藩の城下町時代武家地であった長町に、大正時代に作庭された名園があります。本日ご縁があって、この庭園を観賞させて頂きました。
「主庭、前庭、背戸」で構成されている中、手入れが行き届いた池泉周りを散策、庭石や灯籠、植林の木々と草花・・・。とても見事です。
個人所有の邸宅・庭園ですが、金沢市、石川県、いや日本の代表的な庭園として誇れる「名園」と感じました。
長期にわたる維持管理には、相当のご苦労があったことと思慮します。ぜひともこれから何百年先まで継続・維持し、後世の宝として残して頂きたいとものだと強く感じました・・。
なお、「番いの鴨」が、橋の下で昼寝?していましたが、直ぐに目覚め池の中をスイスイ動いた後、歓迎?の儀式・所作??、雌雄が交互に頭を何度も上下する踊り?を披露してくれました。
※1「足踏み」: 「蓮華躑躅」には毒があるので、馬や羊が誤ってこれを食べると、足踏みして麻痺してしまうという意味や、花のあまりの綺麗さに思わず「立ち止まる」と言う意味もある
※2「躑躅」: 「ツツジ」の他に「テキチョク=足踏みしたり、立ち止まったり躊躇して進むという意味の熟語でもある
※3「番の鴨」: 「二つ揃って一組になる=動物の雄と雌=夫婦」の鴨
《2025.05.08撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 夏来るや 尾山神社に 昼の月 】(なつくるや おやまじんじゃに ひるのつき)
昨日の午後3時半頃、西から東方向に尾山神社を望むと、青空の中に月が見えました。風もなく少し汗ばむ陽気となった金沢市内、薄手のシャツを腕まくりする出で立ちの観光客が詣でていました。
ステンドグラスを配するデザインの「神門」の左上には、あと4~5日で満月を迎える月がくっきりと浮かんでいます。
最近訪れる外国人も、(誰に習ったのか)鳥居を潜る前に頭を下げ「手水舎(てみずや)」では差法にのっとり「清め」て「拝礼」した後に「御朱印」を受ける・・・・最近の日本人よりマナーが出来ている感があります。
なお「御朱印帳」には、神社仏閣のそのものと、観光地に備えてあるスタンプ類が同ページ内にびっしりと押されていました。(御朱印帳と一般的な観光地スタンプとは区別する日本人が多いと感じますが、多国籍の方の考え方とは少し異なるのかな?)
ちなみに、月齢の平均は約29.5日、朔望月(朔=新月、望=満月)と言われる中、この日の月齢は、10.3(昼頃のり値)となっており、「13夜」とも呼ばれます。
※1「夏来る」: 「立夏」から1か月は「初夏」「若夏」「今朝の夏」などと季語を表す
※2「尾山神社(神門)」: 「前田利家公」と「お松の方」を祀る神社と門(先の投稿文参照)
※3「昼の月」: 「昼でも見える(見えた)月」の意
※4「手水舎」: 「てみずや」参拝前に手と口を清める場所
※5「月齢」: 月の満ち欠けの状態を知るための目安(新月からの経過日数)数値
《2025.05.08撮影・05.09投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 武家地跡 流るる水も 五月川 】(ぶけちあと ながるるみずや さつきがわ)
金沢市内を流れる55本の「用水」のひとつである「大野庄用水」は、普段は水嵩も少なくて、もう一本東側を流れる「鞍月用水」両側の商店街を「せせらぎ通り」と称するなど用水は「緩い流れ」なのですが、この日の水量と流れ方は、見ていて怖いほど・・・・。
近くに大正7年設立の「金沢聖霊総合病院」があります。ちょうどキリストの像がこの流れを見下ろす感じの位置を流れる(大野庄)用水です。
訪れた時は、晴天で風もなくまさに「初夏」の爽やかな一日となっていたのに、なぜ流れが急なのか・・・。
観光客の方から「普段からこの用水の水嵩と流れはこんなにすごいのですか?」と質問されました。ちょうどその時、この付近に在住の(高齢者)方が「今の時期は、例年農業用水として水嵩を増やしている時かと思う」「代掻き」や「田植え」に必要となる・・」とのお答えを返していただきました。
※1「武家地跡」: 武家が所有する邸宅があった場所・エリア
※2「五月川」: 本来の意味は梅雨時期で水嵩が増えた川の意
※3「金沢聖霊総合病院」: 「当院の理念」には、「神からいのちを与えられた一人ひとりが、幸せになれるよう心身の癒しのために、キリスト教の愛と奉仕の精神をもって地域医療に貢献します。」とありました。
《2025.05.08撮影・05.10投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 郭公や 何処に鳴けり 広き城 】(かっこうや いずこになけり ひろきしろ)
薄く雲る金沢城内を散策中に「カッコー・・カッコー」と鳥の鳴き声が聴こえてきました。
渡り鳥である「郭公=カッコウ」の鳴き声です。
オスの鳴き声「カッコー」に由来して鳥の名前になったとのこと。また、初夏の訪れを告げる鳥でもあり、この鳴き声をどこかで聴いたことがあると思いますが・・。(メスは「ピッ、ピッ」と鳴きます)
写真の場所は、「河北門」の上部室内に至る階段を上って、北西の方向(JR金沢駅方面)からの眺めです。茶色の背の高いビルは、駅前にある日航のビル、右隅に見えるのは「武蔵が辻」に建つ「ANAホリディ・イン金沢」です。また、下方向に広がる場所は、「金沢城新丸広場」の一角です。
およそ30ヘクタール(東京ドーム6.5個分に匹敵)もある広い城内には、何種類もの鳥の囀りを聴くことが出来ますが、あまりに広くてその姿を見付けるには相当難儀することとなります。
ちなみに、「郭公」自らは子育てせず、他の鳥の巣に産卵し育てさせる「托卵」という習性があり、仮親鳥は自分の卵と見分けが付かず、短期間でふ化する郭公が餌を独り占めにして育つ・・・。
しかも、郭公のヒナは、なんと他の卵(仮親鳥が生んだ卵)を巣の下に落としてしまうとか。(驚き)
※1「鳴けり」: 「鳴く」の命令形「「鳴け」+「り」(完了・存続の助動詞)=「鳴いている」
※2「仮親鳥」: 「モズ」「オナガ」「ホオジロ」など
※3「日航のビル」: ここでは「ポルテ」高さ130mある(県内で一番背が高い)
《2025.05.11撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 惣構え 土居にゆらゆら 大手鞠 】(そうがまえ どいにゆらゆら おおでまり)
金沢市尾張町から橋場町に向かうと、T字路交差点があります。その南東の方角に、「枯木橋」とレトロ建築の「金沢文芸館」が見えてきます。
この「枯木橋」は、以前このHP内で何度か紹介した通り、金沢城を守る仕掛けの「(内外)惣構え=そうがまえ」の様子を伺い知ることが出来る場所のひとつです。
この付近には毎年、「躑躅=つつじ」や「紫陽花=あじさい」などが、その季節ごとの花を咲かせ、通りすがりの市民や観光客の目を楽しませてくれています。
この「構え」下方には(写真下)今も水が流れていますが、常に濃い緑の草花に覆われて、少し見ずらい景観となっています・・・。
晴れて青空の下、眩しいばかりの「大手鞠」が純白の大きな花を魅せてくれました。
※1「惣構え」: 先の投稿文参照
※2「大手鞠」: 「ヤブデマリ」が変異したと言われる「落葉低木」で「装飾花」と呼ばれる雄しべ雌しべが退化し、ガクが花弁のようになった( 葉は楕円形で葉脈が深く刻まれている)
《2025.05.12撮影・投稿》
《お願い》
【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 大手掘り 帽子の鍔に 青時雨 】(おおてぼり ぼうしのつばに あおしぐれ)
朝方まで降っていた雨が上がったものの、まだすっきりとしない空模様の中、金沢城黒門から大手門に向かう大手掘り沿いの小径、朝の散歩を楽しむ人も多く、着物姿の観光客も・・・・。
突然帽子の鍔にバサバサと大きな音とともに何かが当たる音がして、上を向くと大粒の雨?周りを見渡しても誰も傘をさしている姿は見当たらないが、「キャーキャー」という悲鳴があちこちから・・・。
木々の青葉に溜まっていた雨が、風に揺られて落ちてきたようで、手に持った傘を開くまでもなく一瞬の出来事、帽子を被っていなければ髪が相当濡れたことだろうと思います。
この後はなんでもなかったように、徐々に晴れて薄日が射し、すっかり青空へと変化していきましたが、これも自然の成せるわざ・・・。
木々の緑が濃くて空気の美味しい季節、ゆっくり散歩を楽しみました。
※1「大手掘り」: 金沢城の北側に今も一部が残る(先の投稿文参照)
※2「青時雨」: 「青葉時雨(あおばしぐれ)」「樹雨(きさめ)とも称する
※3「季語」: (※2)は夏の季語
《2025.05.12撮影・05.13投稿》
《お知らせ》
【ここを「CLICK」してください】

2025年5月14日(水)から「その32」に移ります