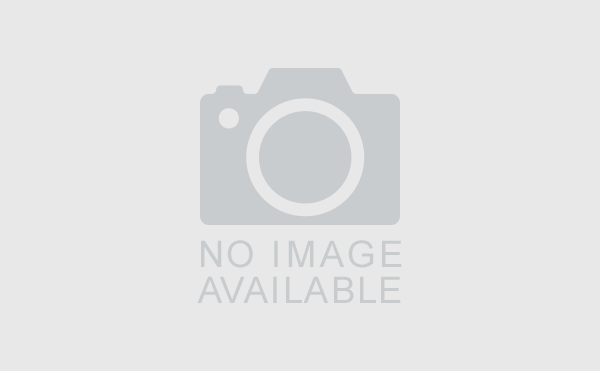<今日の一枚と一句>「その24(2025.01.22~02.04)」

【 いざないや 太陽柱が 初大師 】(いざないや たいようちゅうが はつだいし)
21日の朝、朝日の光が柱のように伸びる「サンピラー(太陽柱=たいようちゅう)」現象が発生した風景をカメラに収めました。
空気中の水分が凍った結晶が、太陽に反射して「柱状」に輝く自然現象の一つとか。
時や場所によってその形は異なるが、「ダイヤモンドダスト」と表現される状態も時折みられるが、東の山から昇る朝日に、これを観ることが出来る現象は希で、とても幻想的でした。
なお、毎年1月21日は、「初大師」(神奈川県・川崎「川崎大師」)「初弘法」(京都・東寺)等と称される「御影供法要」が営まれ、一年最初の縁日は、例月(毎月21日が月命日)より沢山の信者がお参りする日で、骨董や特産物、植木などを販売する多くの露店が並びます。
何か佳きことが訪れるような、そんな気がする一日の始まりでした。
※1「初大師」: 弘法大師の初縁日
※2「太陽柱」: 文中に記載のとおり。(22日の朝刊に関連した記事が掲載されていました)
※3「いざない」: 「誘う(…の古風な言い方)」「勧められる」の意
《2025.01.21撮影・01.22投稿》
《お願い》
【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又は「タップ」してください】

【 雪かきや 余剰在庫が 冬の雨 】(ゆきかきや よじょうざいこが ふゆのあめ)
雨模様となった金沢市内の気温は10度弱、例年の今頃ならば毎朝、玄関先の雪かきが出勤前の一仕事となっていてもおかしくないが・・・・。
しかし、今年は市内中心部に降った雪の量が数センチで、「雪除け」どころか昼過ぎには消雪・・・。
兼六園や金沢城の雪景色を写真に収めるチャンスはかなり少なくて、観光客や写真愛好家泣かせの冬となっています。
市内にある大型ショッピングセンター(ホーム用品を中心に販売する全国チェーン)には、大小さまざまなショベルやスコップの類が数多く展示・販売されています。
冬将軍や、寒気団に関する予報が発表されると、その年によっては在庫がなくなるくらいの売れ行きで、TVニュースにもその様子が取り上げられることも多いのですが、(1月の下旬になっても)相当数の在庫(売れ残り?)が店頭に並べられており、また、当初の設定価格より値下げされた旨の「札」が貼られている状況。
売れ残った在庫商品、来年の冬までお蔵入り?となるのでしょうか・・・ね。
※1「雪かき」: 「雪除け」「除雪」、「雪さらい」とも
※2「冬の雨」: 北国の冬は「雪」や「霙=みぞれ」になることが多い
《2025.01.23撮影・投稿》

【 光る矢が すきま隙間に 寒木立 】(ひかるやが すきますきまに かんこだち)
良く晴れた朝、金沢城・辰巳櫓付近の木立に朝の陽射しが眩しいばかりに入り込んできました。
春・夏にはたくさんの枝葉や絡む蔦の芽吹きなどに遮られて、今の時期ほどに陽が届くことはありませんが、(冬木立の期間中は)幹や枝の間に隙間が出来ることから、より一層光輝いて、まるで火矢がこちらに向かって飛んでくるかのような錯覚を覚えます・・・。
ちなみに、「忍び」など、敵が城内・陣地に入ろうとしても、己の身を隠す茂みが少なく、守備、警護役に見つかる確率が高くなることや、寒さで身のこなしが低下することなどから、敵味方共に係る作戦を猶予した時期だとか・・・。
日の出の時間も徐々に早くなって、春の訪れも少しずつ、少しずつ近づいてます。
晴れた朝は、放射冷却現象で、かなり冷え込みますが、この時期にしか見られない、早朝の金沢城や兼六園の風景をゆっくり散歩で楽しんでみてはいかがですか。
※1「光る矢」: 「朝の陽射し」の様
※2「すきま隙間」: 「冬木立」になり、広くなったと感ずる幹や枝との間隔の様
※3「寒小立」: 「寒中」の寒々とした林の様
《2025.01.24撮影・投稿》


【 西の茶屋 寒さこらえて 袖隠し 】(にしのちゃや さむさこらえて そでかくし)
曇り空の下、西の茶屋街の一角に白い椿(袖隠し)が綺麗に咲いていて、観光客のカメラに収めている姿が多くみられました。
赤い椿も綺麗ですが、白い椿は別の趣があって、この時期に咲くのを楽しみにして待っています。
名前の由来は、どこかの城内に咲いた見事な「白い椿」、本来城外に持ち出すことはご法度の中、あまりにも可憐に咲く椿に見惚れた侍が、袖に隠して(までも)持ち出さしめた花・・・と言うことで名付けられた「名」だとか・・・。
この「句」は、「袖隠し=白い椿」が寒空の茶屋街に綺麗に咲いている様子・・・風景を表す表現と、お茶屋さんの芸妓が一瞬恥じらい?を魅せる仕草や、思いのほか寒くて顔に手をやる身のこなし・・・どちらにも詠むこと、感じることが7できるように、「西の茶屋」を先に置くこにしました。
※1「西の茶屋」: 金沢三茶屋街のひとつ
※2「袖隠し」: 「袖かくし」「袖隠」と表記方法は数種あり
《2025.01.25撮影・投稿》

【 冬雲と 続櫓を 映やす堀 】(ふゆぐもと つづきやぐらを はやすほり)
青空に次々と現れる白い雲・・・金沢城三の丸から鶴の丸休憩館に向かうと、「五十間長屋」から「橋爪門続櫓」」辺りにある内堀の水面に、雲と櫓が写り込んでいて、しばし見惚れてしまいました。
風が強いと水面が波打ち、曇り空だと写り込む「もの」がぼやけてしまいます。
日曜日の昼下がりと言うこともあって、城内には大勢の観光客、特に外国人の方が多く訪れていました。
数グループの人達から道を聞かれたので、ついでにこちらからいくつかの質問をしてみました。
まず、聞かれた「道」は、(これから行こうとする)「近江町市場」の最寄りの出口、「21世紀美術館」、「ひがし茶屋街」に行く(ための)バス停など・・・。
当方の質問は、①金沢の印象②日本での滞在期間③次の訪問先(日本国内)で、その答えは、①美しい街、伝統と近代的なものが上手く調和していて素晴らしい。②2週間~6週間、③岐阜県・飛騨高山、白川郷、東京に戻る。という返事が多かった。。
※1「冬雲」: 「寒雲」「凍雲」など冬の雲
※2「続櫓」: 先に投稿の文を参照
※3「堀」: 「堀」は「鶴丸休憩館」前の内堀り
※4「映し」: 「栄やす=映やす」「引き立てる」「際立たせる」の様
《2025.01.26撮影・投稿》


【 如月や すぐそこまでと 花蕾かな 】(きさらぎや すすぐそこまでと からいかな)
金沢城公園内にある桜の本数は約400本、例年の開化時期はまだまだ先、3月下旬の頃ですが、その時のための準備に入ったのかな?と・・・・。
百間堀の内側、石川門から続く鉄砲狭間付近に植林の桜の木、枝の伸びとともに小さな蕾が少しずつ現れてきました。
晴天の城内、風も強く吹かない昼下がりの時間帯は、まるで温室のように暖かくて心地よい空間、静かに読書でも・・・・と、つい考えてしまいます。
「小さな春」を草花の姿に見付ける・・・そんな植物観察の散策が楽しめる時期に入りましたね。
※1「如月」: 「二月」の異称
※2「花蕾」: 「からい=花と蕾」
《2025.01.26撮影・01.27投稿》

【 枯庭に 借りて石垣 わび茶かな 】(かれにわに かりていしがき わびちゃかな)
寒中の「雪吊り」、お役目を果たす機会もなくて、のんびりと「ひなたぽこ」をしているような雰囲気の玉泉院丸庭園、四季折々に木々や草花、鳥たちが変化を齎してくれて、一年中楽しむことが出来る「池泉回遊式庭園」です。
その傍らにある「玉泉庵」では、お抹茶を頂くことが出来ます。
(この風景撮影時には数組のお客様がお茶を楽しんでいる様子がうかがえました。)
この庭園は、石垣を「借景」として採り入れて、池底から石垣の最上段まで20mを超える立体的な造形美を眺め楽しむことが出来ます。
ちなみに「わび茶=侘茶」という言葉は、江戸時代からで、「茶の湯」と同義と思われる「侘茶湯という表現も見られる」との解説があります。
※1「枯庭」: 「枯園=かれその」「冬の園=ふゆのその」「庭枯るる」などと同意
※2「借りて石垣」: 石垣を「借景」とした景色の様
※3「侘茶」: 文中のとおり
※4「玉泉院丸庭園」: 先に投稿文参照
※5「撮影場所」: 「いもり坂」の中ほど
《2025.01.26撮影・01.28投稿》

【 誰の手か ポストの上に 雪だるま 】(だれのてか ぽすとのうえに ゆきだるま)
昨晩から雷光と霰、静かになったと思ったら、明け方に降った雪が少し積っていました。
にしの茶屋街にあるお茶屋さんの竹垣傍に設置のポストの上に、小さな雪だるまがふたつ並んで置かれていました。
誰が作ったのか・・・(南国からの)観光客?、幼子と母親?・・・などと次々に想像が膨らみます。
今冬の金沢市内、昨日までの積雪は数センチでしたが、向こう数日間の天気予報によれば、本格的な降雪・積雪になる恐れがあるとのこと。
山手にあるスキー場では、営業に差し支えないほどの積雪があると時々ニュースに流れていることから、夏場の「水不足」は避けられそうかと・・・。
なので、せいぜい雪景色が楽しめる程度の積り方で、立春を迎えたいものだと願っていますが・・・・。
《2025.01.29撮影・投稿》


【 水雪や 信州人の 足重し 】(みずゆきや しんしゅうびとの あしおもし)
北陸・金沢の冬、水分を多く含んだ雪と融雪装置により、更に歩道や交差点付近の雪が解けてシャーベット状になり、また深みがあって、長い靴や完全防水仕様の履物が必需品となります。
観光で訪れた方の履物が、単なる防寒仕様である場合、街歩きの際には至る所でご苦労されることに(靴の中に浸水する)なります・・・。
長野県から観光に来られた方は「雪には慣れているが、ここの雪は水分を多く含んでいて、横断歩道を示すペイント部分が特に滑るので危ない」と少し困り顔に・・。
融雪装置からの散水などで、あちこちに深い水溜まりが出来ていて、細心の注意を必要とするほか、用心しないと車からの「水はね」にも気を配らないと・・・。
今回の撮影場所は、橋場町の小路や交差点付近ですが、あちこちにある大小の坂道での転倒にも十分注意が必要です。
なお、金沢観光の必需品?「傘」に加えて、「ゴム長靴」も無料で借りることが出来るサービスがあります(「石川県金沢観光情報センター」で無料レンタルが可能)のでご利用くださいね。
※1「水雪」: 水分を多く含んだ雪
※2「信州人」: ここでは長野県からの旅行者の意
※3「足重し」: 歩きにくい様
《2025.01.29撮影・01.30投稿》

【 せせらぎの 名前いずこや 冬の水 】(せせらぎの なまえいずこや ふゆのみず)
金沢市の繁華街、香林坊の裏手に「鞍月用水」という小川が流れています。昨晩から降った雪の影響か、取水口の調整具合なのかは分かりませんが、いつもの流れ方に比べてものすごく早く、また雪の塊も流れて水嵩も高く勢いがありました。
(金沢市内に流れる用水は55本、総延長は150キロメートルにも及ぶと言われています。)
日頃の流れは穏やかで「せせらぎ」・・その名を付けての「せせらぎ通り」、いろんなお店が軒を並べているエリアです。
「大雪に注意が必要」との天気予報でしたが、朝方の気温は少し緩んで、氷点下とはならず降雪量も少なくて、日ごろからの散歩には支障のない・・・と言いたいところですが、やはり湿った雪の歩道はやはり歩きにくくて・・・。
さて、明日から2月、あっという間に「2月は(に)逃げるように」過ぎていくと言われています。元気で楽しく、いろんなことにチャレンジしたいと考えています。
※1「せせらぎ」: 細い小さな川、「水のせせらぎ=浅瀬などを流れる水の音」
※2「冬の水」: 「寒中の水」は特に雑菌も少なく、寒に入って9日目を「寒九の水」といい、薬や酒を造るには適しているとか
《2025.01.31撮影・投稿》

【 風花や ひらりきらりと 朝日映え 】(かざはなや ひらりきらりと あさひはえ)
晴れているのに、ひらりひらりと雪の花・・・防寒具の肩先に落ちてしばらくすると溶けてしまう・・朝日が当たり、溶けて消える一瞬、キラリと光り輝く様子はとてもとても綺麗です。
マイナス気温とはならなかった朝の金沢市内、城下町独特の入り組んだ小路には、ちらつく雪が融雪装置からの散水がなくとも、地に着くまでに溶けてしまいました。
毎年この時期から春までの間に繰り返される朝の風景ですが、その日の空模様によっても風景が変化するので、飽きることのない朝散歩の楽しみの一つです。
※1「風花」: 晴天にちらつく雪
※2「ひらりきらり」: ひらひらと舞い落ちる雪片に朝日が当たる様
《2025.02.01撮影・投稿》

【 道の辺に 地図を広げて 寒霞 】(みちのべに ちずをひろげて かんがすみ)
金沢市内の繁華街、片町スクランブル交差点付近に、旅行者と思われる若い女性数人のグループが、広げた地図を指さしてワイワイ・・・。
殆どの若者は、スマホの地図アプリを駆使してお店や観光スポットを検索するのかと思っていましたが、最近珍しい光景に出会いました。
地図と言えば、カーナビの無かった頃、道路地図を頼りに事前にルートを調べ、移動中は道路標識を見ながらの運転・・・。
迷いながらも目的地に着いた喜び、ドライブが楽しめた時代でした。
今では、知らない土地を訪ねる時、カーナビは必需品となりましたが、そのためか、国道や府県・市道路の番号(ルート№)や、道順などを覚えることが少なくなってしまいました。
国産H3ロケット5号機(日本版GPSみちびき搭載)の打ち上げが成功しました。
これで同種の運用は4基、最終的には7基体制になるとか。ますますカーナビなどを含めて、我が国の安定的な測位システム運用とその精度が上がるとのことですね。
ま、デジタル技術の進歩は多方面に好影響を与えてくれると思っていますが、時には、道路地図を片手のアナログ旅行、スマホやカーナビに頼らず・・・旅をしてみたくなりましたが、はたして・・・。
※1「道の辺」: 「みちのべ=道辺=みちべ」道のほとりの意
※2「寒霞」: 冬の暖かい日の大気中に薄くたれこめた「もや」の様
《2025.02.02撮影・投稿》

【 暮れ六つや 飛び切り燗に 月冴ゆる 】(くれむつや とびきりかんに つきさゆる)
暮れ六つ(現代の夕方6時)の頃、西南の空に明るく輝く星、暮れの明星(金星)は、この時期でなくとも観ることが出来ますが、月と金星と土星を一緒に観ることが出来、これを線でつないだ形が「くの字の逆」に観える・・・・そんな天体ショーは、冬空が晴れて空気の澄んだこの時期が見頃かと・・・。
晩酌片手に冬の夜空をゆっくり眺めることが出来る環境は、この時期にはなかなかないことから、しばし長めの天体観測を・・・。
晩酌は少々嗜む程度ですが、昨晩はなぜかしら「飛び切りの熱燗」になってしまい、フウフウと冷ましながらのお酒タイムになりました。
ちなみに、燗酒の温度によって、「日向燗=30℃」「人肌燗=35℃」「ぬる燗=40℃」「上燗=45℃」「熱燗=50℃」「飛び切り燗=55℃」「真宗寺燗=55
~65℃」とか・・。
今晩から数日間は「今冬一番の警報級大雪」との予報が出ていることから、昨晩のように夜空、月・星を眺めることが出来ないのかなと・・・。
※1「暮れ六つ」: 文中説明のとおり
※2「「飛び切り燗」: 文中(温度)区分のとおり
※3「月冴ゆる」: 寒さが厳しく、(透き通ったような)凛とした月の様
《2025.02.02撮影・02.03投稿》

【 城が雪 もとより白し 海鼠壁 】(しろがゆき もとよりしろし なまこかべ)
今冬最強の寒気来襲予報の日本列島、ここ金沢城の屋根(鉛瓦)が雪を被り、真っ白に雪化粧・・・。
百間掘りを挟んだ手前(兼六園側)には、春の開花を待つ桜の枝が凍てつき、暦の上の「立春」とは思えない姿になっています。
幸い暴風雪とはならずに、しんしんと静かに降る雪だったので、石川門から続く塀の壁「海鼠壁」に囲まれた瓦の形がくっきりとして、とても綺麗に見えます。
ここ数日間降り続くとの予報が出ていますが、輸送機関(新幹線、高速道路など)に大きな乱れ、影響が少ないことを祈るばかりです。
※1「海鼠壁」: 金沢城独特の壁工法(四角形の平瓦を張り合わせて漆喰(白色)で蒲鉾型に固める方法
※2「立春」: 二十四節気の始まりで、今年は2月3日(月)、暦の上では「春」
《2025.02.04撮影・投稿》

2025年2月5日(水)から「その25」に移ります