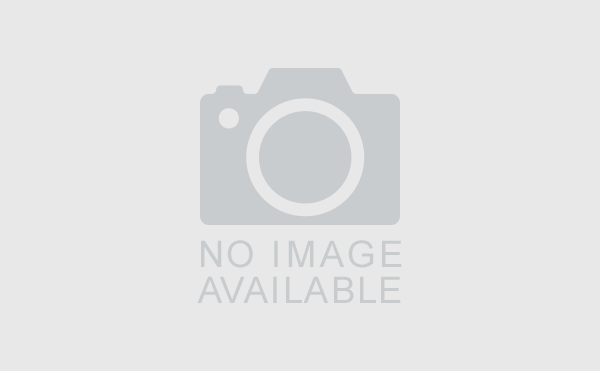〈今日の一枚と一句>「その23(2025.01.08~01.21」

【 初点前 躙る膝さき 茶碗かな 】(はつてまえ にじるひざさき ちゃわんかな)
茶の湯の盛んな地域では、初めての茶事を切っ掛けとしてデビューする茶碗のお披露目があったりします(自慢しー?)茶道にある決め事のひとつに、「立ち上がらず膝のみで動く所作」(表現が誤っていたらごめんなさい)、新しい茶碗を「亭主」が(嫌味なく)そっと置いたのを皆がわかって、にじり寄って褒め称える場面、毎年繰り返されることですが・・・。
今年の新参は、「永楽即全 仁清黒七宝茶碗」なんとか(^^;
この年になっても、「やきもの」と「侘び寂び」「俳句・川柳・短歌」全くの素人・・・。
今年は少し「広く狭く奥深く」と行きたいものですが・・・。
※1「初点前」: 新年に初めて茶事を行うこと・・・かな?
※2「躙る」: 膝で動く所作「にじり(よる)」とも
※3「茶碗」: 名のある茶碗で少なくとも現在の価格で30万円程の価値があるかと・・
《2025.01.08撮影・投稿》
《お願い》
【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又は「タップ」してください】

【 松枝の 沙汰を受けたり 雪垂り 】(まつえだの さたをうけたり ゆきしづり)
日本海側を中心として、今期最強の寒波襲来とかで、気象庁が会見を開いて注意を促すほど強烈に影響を及ぼしかねない気象状況となっていますが・・・。
金沢市内長町の「武家屋敷跡」、今朝の様子をウオッチングしてきました。
雪模様を撮影する機会・風景としては、今冬二回目となる?積雪の様子、土塀の上や木々に数センチ積っていました。
閑静な中を散策すると、突然「バサッ!」という音がして、辺りを伺うものの・・それ以上の音も気配も感じられず、また人の往来もなく、とても静か・・・・。
たぶんですが、松の木などの植木の枝葉に積った雪(土塀の内側)が落ちた音かな~~とも・・・。
「不要不急の外出を避けるように」とのことでありますので、安全が確保出来るまでの間は、(自宅にて)冬眠としますかね・・・(^^;
※1「松枝」: 松の枝の意
※2「沙汰」: 「挨拶=あいさつ」の意
※3「雪垂り」: 木の枝などに積った雪が、落ちたり散ったりする様子
《2025.01.09撮影・投稿》

【 バス乗り場 遅延ありなん 雪しまき 】(ばすのりば ちえんありなん ゆきしまき)
融雪装置が整備された金沢市内、バスの路線上には雪はみられないものの、小路に入ると、それなりの積雪があって歩きにくく、油断すると転倒しかねないことから、観光客の「ペンギン歩き」も見られた金沢駅周辺・・・。
「強烈寒波襲来」とのことでしたが、昨晩からの積雪は想像していたよりも少なくてよかったのですが、時折強く吹く風に雪が吹雪となって、傘をさすことが困難になることもありました。
午後3時を回った頃に、バス時刻を確かめると待ち時間が15分ほどありましたが果たして遅延してはいないだろうか?と・・・。
山手の方を経由するバスは少し遅延している様子でしたが、当方のバスは時間通り発車することが出来ました。
ちなみに、朝の通勤時間帯では、路線によってはダイヤに乱れが発生していたとのこと(同乗者の会話から)でした。
※1「遅延ありなん」: 遅延も(当然)するだろう、「然(さ)もありなん」の意
※2「雪しまき」: 「しまき=しまく=巻く」「吹雪が激しく吹き巻く」様
※3「ペンギン歩き」: 歩幅を小さくして、そろそろと歩く(歩き方)安全歩行の意
《2025.01.10撮影・投稿》

【 狛犬を お道化てみせて 雪帽子 】(こまいぬを おどけてみせて ゆきぼうし)
正月に詣でる神社の中で、加賀一の宮「白山神社」は、正月元旦から左義長までの間、毎日訪れる人が絶えなくて・・・・。毎年少し落ち着いた頃に詣でることにしています。
正月の一旬を過ぎた今日でも、駐車場は満車でした。
慌てずゆっくりと空きスペースを探しながらしばらく待って駐車、お参りすることが出来ました。
「狛犬」さんは、全身に雪を被っていて、まるで「雪帽子」を着けたお姿の様で、見方によっては「かわいい~」と、若い女性達に騒がれそうな・・・・・。
鼻の頭に「ちょこん」とのった雪、なかなか拝見することのないシーンだったので、「パチリ!」ました。
※1「狛犬」: 以前投稿の関連文参照
※2「お道化てみせる」: 「観る人を笑わせるような姿形」の意
※3「雪帽子」: 「雪を防ぐため頭から体の上部にかけて被るもの」だが、既に被った雪の形が、まるでその「帽子」のような様
《2025.01.11撮影・投稿》

【 冬日和 漫ろ歩きか 雀二羽 】(ふゆびより すずろありきか すずめにわ)
久しぶりの朝日、放射冷却現象で所々にブラックアイスバーンがあっても良く確認しないと判らないほど凍てついたツルツル歩道、通行人が数人転倒する場面も見られた金沢市内の朝でした。
ここ数日の冬空・強風・降雪の中、どこに潜んでいたのか、雀が二羽・・・とことこ?ヨチヨチ?歩いていました。
警戒心からか、低木の下から少し出て様子を伺い、直ぐに引き返すような仕草を見せて、安全だと判ると、比較的長い距離を歩みます。
朝の時間帯なので、鳥たちの朝食かとも思えたのですが、それにしては比較的ゆっくり歩んでいて、人と同じように貴重な日差しの中の朝散歩を楽しんでいるようにも見えました。
※1「冬日和」: 「ふゆびより=冬晴れ=冬晴るる」との表現もある
※2「漫ろ歩き」: 「すずろありき(「・・あるき」ではない」=とりとめなく歩き回ること、そぞろ歩きとも
※3「撮影場所」: 「西茶屋観光駐車場」の低木(雪吊りが施された)付近
《2025.01.12撮影・投稿》

【 香箱に 猫が座りて 日向ぼこ 】(こうばこに ねこがすわりて ひなたぼこ)
この三連休は天候に恵まれて、日中に陽が射す時間帯もあって、特に振り袖姿で臨む「成人式」には、足元を気にしなくとも良かったと思われる金沢エリアでした。
ご近所の雌猫(尻尾のみが三毛)も、エアコンや炬燵などの暖房よりも、太陽熱を好んだのか、久しぶりに姿を見せて、しばし「甲羅干し?」よろしく「香箱座り」で「日向ぼこ」を楽しんでいる様子がとても微笑ましく映りました・・・・。
隣人(飼い主)によると、今の時期、炬燵の中が常宿で、家人が起きている間は炬燵の中、寝る時間になるとタイマーをセットして寝室に行くも・・・。朝には主の布団の中か、掛布団の足元に来ているとか・・・・。
タイマーが切れて寒くなったからか?はたまた寂しくなっての所業か?・・・猫の行動・考え方は、よくわからないそうです(^^;
ちなみに「猫行火=ねこあんか」とは、猫の暖かさを「暖房」として利用するとの意味ではありませんので念のため(^^;
※1「香箱座り」: 「香りのする品を入れる箱の形」のように見える猫の座り方
※2「日向ぼこ」: 「日光に当たり暖まること」「日向ぼっこ」とも言う
※3「三毛猫」: 三毛猫は高い確率で「雌猫」と言われている
《2025.01.13撮影・投稿》

【 都路に 夢かうつつか 咲く椿 】(みやこじに ゆめかうつつか さくつばき)
昨年、北陸新幹線は敦賀駅まで延伸しており、この先は京都、大阪方面に向けての着工が急がれる所ですが、既に八年以上前には決定していたはず?の「小浜ルート」が、建設費の高騰や、京都市など関連する自治体からの反対(難色)を示されており、急遽「米原ルート」が代替案として浮上するなど、そのルート選択に当たっては、国や議員、自治体の動きが昨今のニュースとなっています。
JR金沢駅の兼六園口(新幹線乗降口側に近い)出口にある小公園内に、「椿の花」が咲いていました。
春の季語ともなる「椿」、調べてみると、どうやら「海棠椿=かいどうつばき」のようでもあって・・・。
「海棠椿」となると、晩春…どちらにしても「春」に咲く花のイメージで、今の時期にポツンと一輪咲いた花、不思議な感じがします。
大阪・神戸方面からは「サンダーバード号」、名古屋方面からは「しらさぎ号」一本で、乗り換えなしに北陸方面にアクセスできた各特急に比べて、「新幹線」は敦賀駅での乗り換えが必要となり、相当不便になったとの利用客の声も多い。
いずれのルートを選択するにしても、早く着工に動かなければ、その分開通が遅れる訳ですね・・・。
花(「椿」「海棠=かいどう」)が、都(京都)まで開通した夢でも見ているのか、春を待たずにもう開花し始めました。
※1「都路」: 「都(ここでは京都) に通ずる道」の意
※2「夢うつつ」: 「ぼんやりしている状態」「夢とも現実とも区別がつかない状態」の様
※3「海棠椿」: 外来(海を渡って伝わる)種で、中国名は「越南抱茎茶」等、種々あり
《2025.01.14撮影・投稿》

【 兎走烏飛 破魔矢飾りて 月半ば 】(うとそうそ はまやかざりて つきなかば)
つい先日まで「大晦日」だ「正月」と言っていたところですが・・・・・もう15日になり小正月、
「立春」は、もうすぐそこまで・・・。
「月日の経つのが慌ただしく早い」ことの表現で、「兎走烏飛」、「光陰矢の如し」など、昔から時間経過が早く、何かを成しておけばよかったと後悔する様子や言葉として使われている。
そうならないためには、常日頃から、自らを律し物事を先へと進めておくべき・・・と。
若い時は、それほどまでに早く時間が過ぎたという実感がなかったように思えるが、年を重ねるごとに、1日が、1週間が、ひと月が早くなり、そんなこんなで四季の移り変わりも早くなり、そして1年があっという間に過ぎ去る・・・このように思えてならない。
このHPは、昨年(R6年)の1月15日に立ち上げてから、「今日の一枚と一句」を毎日更新し、(おかげをもちまして)今日から2年目に入りました。
この間の投稿写真は400枚弱、俳句、川柳、短歌風の投稿数は365句を超えました。
この先も「歳月人を待たず」: 時間は自分の都合とは関係なく、「刻々と過ぎていく」もの・・・「刻々と過ぎていく」ものなら、その時々の風景や心に思い浮かんだことを「時事刻々を淡々と刻む」に心掛け、継続していきたいと思っています。
※1「兎走烏飛」: 月には「兎」、太陽には「烏」がいるという中国の伝説から「慌ただしく過ぎる」の意
※2「破魔矢」: 正月の縁起物で神社・寺院で授与される(買い求める)もの
※3「月半ば」: 半月、ここで「小正月」を用いると※2「破魔矢」と、季重りとなるので、この表現とした
《2025.01.15撮影・投稿》

【 寒梅を そっと添えたし 城の朝 】(かんばいを そっとそえたし しろのあさ)
夜半にはなかった雪が、明け方に降り積もって「白いお城」が雪化粧で、より白くなった景色・・・。空にはまだ雪雲が残るものの、朝日があたり、年に数度見ることが出来るかどうかというほどの絶景・・・。
出来る事なら、ワンポイントで紅の色した花物でも添えたいところ。ならばと浮かんだのは「この時期に咲く寒梅、前田家家紋の「梅鉢=うめばち」に採用されている「梅」が似合うのではないかと・・・。
まだまだ「寒」最中、大寒までもまだまだ・・・厳しい寒さが続く中、早朝にもかかわらず、大勢のカメラマンが、あれこれレンズを取り替えながら、静かな中にシャッター音が響いてきました。
※1「寒梅」: 寒中に開花する梅
※2「梅鉢の家紋」: 「加賀藩前田家」の家紋、先に投稿の文参照
※3「城の朝」: 鶴の丸休憩館辺りから金沢城五十間長屋(菱櫓、橋爪門続櫓)を見る
《2025.01.16撮影・投稿》


【 湯布院に 目覚めて朝や 寒の霧 】(ゆふいんに めざめてあさや かんのきり)
「阪神淡路大震災」発災から今日で30年が過ぎ、「追悼式典」が挙行されている様子がライブニュースとして流れていました。
大きな地震として「阪神淡路大震災」(1995年)、「東日本大震災」(2011年)、「熊本地震」(2016年)、「能登半島地震」(2024年)は記憶に新しいところであるが、実は、これ以外にも比較的大きな地震が相当発生しており、2016年には大分県の「湯布院」でも震度6弱(M7.3)の地震が記録されました。
昨晩11頃のニュースで、地震に対する備えの大切さを説く専門家の話が心に残ったのか、夢の中に以前訪ねた「九州エリア(熊本、鹿児島、大分)」が出てきました。
目覚めてから夢のストーリーの半分以上は残っていなかったが、「湯布院の金鱗湖」と「湯布院岳」・・。
幻想的な「朝霧=冬霧=煙霧=寒の霧」(時節によって呼び方は異なると思うが)風景が鮮明に思い出されて、撮影した写真データーを探してみました。
(金鱗湖まで徒歩で数分の宿に泊まり、まだガス燈?が燈っている頃から出かけ、沢山写真に収めました。)
いつどこで発生するかわからない災害、今日は「非常持ち出し袋」の点検・補充を済ませました。
※1「湯布院」: 大分県の温泉地、観光地として人気があります
※2「寒の霧」: 冬に出る霧
《2012年撮影・2025.01.17投稿》

【 佐保姫も 待って蕾むか 木蓮花 】(さおひめも まってつぼむか もくれんか)
雲一つない青空となった北陸金沢、放射冷却現象なのか、朝方の寒さは厳しいものがあったものの、日中の陽射しは強烈で、お嬢さんたちの日傘姿もチラホラ・・・。
ここ長町公民館の敷地内に植林の「木蓮」、春に向けて蕾がより大きくなったように思えて・・・。
隣にある雪吊りに支えられている木々をしり目に、小さな蕾から大きな蕾まで、まるで少年から青年に至る成長、一夜にして伸びて骨格・節々が痛みむ人間のようにも見えるほど、元気な姿が青空に映えていました。
春の訪れを間近に感じさせてくれたモクレンの蕾、春にはきっと薄紫の大きな花と香しいかおりを届けてくれるのでしょう・・・・。
※1「佐保姫」: 「さほひめ」は春をつかさどる女神
※2「木蓮花」: 木蓮の花(もくれんか)
※3「花言葉」: 「忍耐」「威厳」「崇高」「自然えの愛」など多数あり
《2025.01.18撮影・投稿》

【 白妙の 山と城かな 寒の晴れ 】(しろたえの やまとしろかな かんのはれ)
真っ青の空に金沢城の菱櫓と北東方向に見える雪を被った山々、どちらが白いかを互いに競い合っているかのようにも思え、寒中にもかかわらずあちこちにシャッターチャンスの画角素材がありました。
城の北東が鬼門に当たることから、石垣の角等には「鬼門外し」が施され(これに関連しては以前投稿済み)ていますが、雪を冠した山は魅力的です。
連日晴れる予報となっておりますので、今しか見れない風景を散歩がてらに出かけようと思います。
※1「白妙の」: 白い色の意から、「雪」や「雲」などにかかる
※2「鬼門外し」: 前の投稿文参照
※3「寒の晴れ」: 「寒中」によく晴れた様子の意
《2025.01.18撮影・01.19投稿》

【 銀杏の木 髪を整え 春を待つ 】(いちようのき かみをととのえ はるをまつ)
秋に見事なまでの黄色葉を魅せてくれた銀杏の木、寒中の晴れ間に見上げると、植木職人の成せる業か、枝が短くカットされ、とても寒そうに見えます。(金沢城の甚右ヱ門坂を登った場所にある駐車場にて撮影)
銀杏は、「裸子植物」で落葉性の高木、銀杏が食用として流通する・・・程度の知識しかありません。
しかし、「ジュラ紀(2億年~1億5千万)」には全世界的に繁茂したとかで、今に種を残していることから少々の寒さには何ともないのかも知れませんね。
物の本によると、「銀杏の木は冬ごもり(冬眠?)」するという表現があちこちに出てきます。
興味を持ったので、少し紐解いてみたくなりました。
※1「銀杏の木」:「落葉樹」で冬は陽が弱くなるので光合成が出来なくなる(冬眠)
※2「髪を整え」: 人間で言うところの「散髪」(園芸上必要な措置?)された姿の様
《2025.01.18撮影・01.20投稿》

【 青と白 大寒空に 山河添え 】(あおとしろ だいかんそらに さんがそえ)
プロ級の腕前を持つ写真愛好家の友人から、「立山連峰」と「常願寺川」に架かる「富山地方鉄道の鉄橋」を走る電車を捉えた素晴らしい一枚が届きました。
「大寒」、今年は「寒の入り」からの天気が荒れることも少なくて、比較的穏やかな印象のまま・・・まだまだ2月に入っての「明け」までは油断できませんが・・・・。
毎年この頃の立山連峰と電車を捉えた写真を送ってもらっていますが、その年によっては、大雪の富山市内の風景であったりしますので、今回の「一枚」は「シリーズもののコレクション」に加えて大切に保管することにしました。
※1「青と白」: 晴天の空の色と雪に覆われた白い山のコントラスト
※2「大寒」: 今年は1月20日、明けは2月3日頃?
※3「立山連峰」: 3000mクラスの「大汝山」「雄山」「富士ノ折立の三山を合わせて「立山」と呼ぶ
※4「山河添え」: 空の青さに更に立山連峰(白)と常願寺川(青)を加えた景色の様
※5「常願寺川」: 3000mを長さ56キロの間に降りきるのは世界的にみても有数の急流河川といわれる
《2025.01.20撮影・01.21投稿》

2025年1月22日(水)から「その24」に移ります